乳児の運動発達:診かた・考え方
Key Words : 乳児健診 運動発達診断 発達変異 脳性麻痺
本資料は、一般小児科医や保健師などの専門職を対象として、専門医の立場で記述してあります。用語が分かりにくい・読みにくいとか、わが子の運動発達についての相談などがある方には[ご質問など]でのご回答を考慮します。
ただし、運動発達はご本人を診察してこそ責任ある評価・家庭生活支援等が可能になります。メールでは限界があることをあらかじめご了解ください。
乳児健診における運動発達に関しては,単に,頚定・座位獲得などの運動発達指標(mile-stone)通過が遅れることのほかに,月齢に応じた発達変異(developmental variation)の問題がある.即ち,他児との比較で個人差が目立つ場合において,保護者が心配を訴えることがある.一方,健診担当者に異常の可能性を指摘されて,保護者が心配をすることもある.或いはまた,保護者は内心は心配していたが,健診担当者に相談をせず,しかし,健診の場において,担当者からその心配事項を指摘されて,保護者が不安を増幅させることもある.
著者は,鳥取県東部医療圏において,乳児の運動発達評価と療育の責務1~4)を担っている.多様な症例の経験を基に,乳児健診の質の向上を願い本稿を記した.
乳児の運動発達と問題になりやすい徴候
乳児健診における運動発達に関しては,単に,頚定・座位獲得などの運動発達指標(mile-stone)通過が遅れることのほかに,月齢に応じた発達変異(developmental variation)の問題がある.即ち,他児との比較で個人差が目立つ場合において,保護者が心配を訴えることが�ある.一方,健診担当者に異常の可能性を指摘されて,保護者が心配をすることもある.或いはまた,保護者は内心は心配していたが,健診担当者に相談をせず,しかし,健診の場において,担当者からその心配事項を指摘されて,保護者が不安を増幅させることもある.
健診等で問題になりやすい発達変異を図1にまとめた.生後2か月前後において,“反り返り”の訴えがある.4か月前後では“うつ伏せを嫌う”との心配を聞く.5か月を過ぎると“寝返りをしない”との相談を受ける.
さらに,6か月前後以降の乳児期を通じて,“下肢を突っ張らない”ことや,その後,“座位移動(shuffuling)”を続けて,“立位姿勢をとらない”ことの悩みを聞く.
或いは,“座位姿勢で安定せず,後方に倒れる”とか,“這わない”こと,さらに,“這いの姿勢に左右差がある”ことの訴えもある.
立位獲得段階においては,かかとをつかないで“つま先立つ”などの心配を聞く.
これらは,運動発達の指標,即ち,頚定,寝返り,座位,這い,つかまり立ち,伝い歩きといったmile-stone 通過の遅れに留まらない,いずれも変異と評価し得る心配・相談事項であり,脳性麻痺,知的障害等の発達障害との鑑別が求められる.

以下,各々について概説する.
仰臥位姿勢の発達
運動発達変異を理解する上で,仰臥位姿勢の発達過程を熟知しておく必要がある(図2).
即ち,胎児期は狭い胎内において,屈曲位姿勢が主体となる.そして,出生後には伸展位が優位となる.即ち,背筋群優位の「第1伸展期」であり,頚定獲得期に相当する.肩は外転し,足蹠は床面に着地していることが多い.
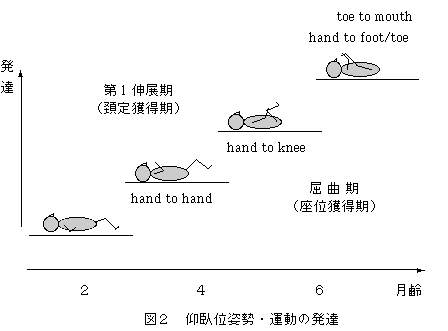
生後4か月頃になると,手と手を合わせて遊ぶ機会(hand to hand)や下肢を屈曲している時間が長くなる.月齢と共に,次第に,下肢の屈曲位姿勢が多くなり,手で膝に触れたりする(hand to knee).これらは,おむつを外した時に顕著になるので,診察上留意することになる.仰臥位姿勢において,殿部の挙上(bottom up)は,正常発達児では例外なく認められるので重要である.
当然,個人差があるが,生後5~��6か月になると,手で足趾を持って遊ぶ(hand to toe)ようになり,bottom up が目立つ.その持続時間が長くなり,足趾を口に持っていったり(toe to mouth)もする.この時期は,屈筋群優位の「屈曲期」であり,座位姿勢獲得期に一致する.手で足を持って遊んだり,足趾を口に入れたりする姿勢・遊びをもって,仰臥位姿勢が完成する.
それへの到達時期の早い・遅いや,持続の長短はあるが,正常児では必ず獲得・到達するため,運動発達評価上極めて重要である.そして,hand to kneeやhand to toeの姿勢を,その獲得前に,目を見つめ,あやしながらとらせることは,運動発達を促すことにもなる.
なお,痙性タイプの脳性麻痺では,hand to toe などの姿勢・遊びの獲得に至らないことが多い.例外的に,minor CP(cerebral palsy)に属する非常に軽い痙性麻痺児は,hand to toe を獲得し得る.極稀には,3歳児健診においても痙性麻痺が見のがされる例がある.
片麻痺のグループでも,仰臥位姿勢でのhand to kneeやhand to toeの観察は早期診断に有用である さらに,両手離しで,背が伸びて座位姿勢が安定する生後7か月頃以降には,hand to toeやtoe to mouthの機会は減り,再び伸展筋群が優位の「第2伸展期」となり,立位化に向かう.
非対称性頚反射に関する諸事項
非対称性頚反射(assymmetrical tonic neck reflex,ATNR)は,正常児では一過性の原始反射である(図3).即ち,生後1か月過ぎから2か月頃に目立つ反射姿勢であり,顔が向いた側の上肢が伸展し,後頭部側の上肢が屈曲挙上する姿勢をとる.この姿勢は原則として両方向に認められるが,中には,一側方向に顕著な例がある.
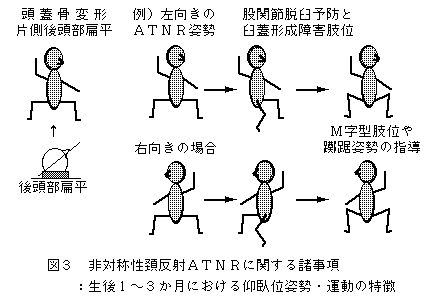
ATNRが顕著な例では,新生児期~乳児早期の頭蓋骨の縫合が開いているがために,かつ,自発的な抗重力運動が乏しいため,顔の向く側の後頭部が,しばしば扁平に変形する(図3).とくに,冬季の日照時間が少ない山陰地方では,4・5月頃に頚定獲得期を迎える乳児において顕著となる.
これに関しては,頭蓋骨の変形が保護者の心配事となり,一方,股関節脱臼位を取る例(図3)が診察医側の課題となる.なお,生後3か月を過ぎると,反射姿勢としてのATNRは消失しているが,一側の後頭部扁平の影響を受けて,左右差のある姿勢が継続している例に遭遇する.
頭蓋骨の変形は,睡眠時に自発的な頭位変換が可能となり,立位姿勢が生活の主体となるにつれ,かつ,頭囲の発達に伴って,徐々に目立たなくなる.一側の後頭部変形が著しい例では,顔面の非対称も認められるが,遅くとも学童期には目立たなくなる.一方,後頭部の扁平を阻止する目的で,ドーナツ枕等を用いる指導がなされるが,これは頚部を屈曲位に強いることになり,呼吸生理の面から望ましくない.また,頭蓋骨の変形を防ぐためにという腹臥位保育は,それが乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスク因子であるため勧められない.病的ではなく,心配することではないことや,顔の向きにくい側から声かけをしたりの配慮をするように話すことになる.
ATNR姿勢が強い例では,下肢にもその影響が認められ,股関節脱臼位を呈する例があり,生後3週頃から遭遇する(図3).即ち,後頭部側の股関節が内転・内旋し,大腿骨の軸が脱臼位を呈する例である.今日,股関節脱臼の大半は,家族歴�があることや女児に多いこともあるが,生後の股関節の発育環境に関する要素が大きいとされている.股部に余分におむつを挟むなどして,股関節を「M」字型肢位に保つことや,躑踞姿勢で抱くことなどの育児指導をする.
反り返り姿勢に関する諸事項
反り返りが強い例の特性を,正常・病的の評価の鑑別に有用な所見を含めて,表1にまとめた.第1伸展期に相当する生後2~4か月に限られるが,程度が目立つ場合,発達診断を求められ,その変異の強さを記録する観点からearly dystonia と記載している.即ち,錐体外路症状を伴う脳性麻痺における dystonia との鑑別が必要であり,発達変異の一型としての early dystonia の記載である.
表1 反り返りが強い例(early dystonia)の特性
・ 運動発達上では、第1伸展期に相当する時期(頚定獲得までの期間:体幹背側伸展筋群優位の時期に相当)
・ 保護者が、反り返り姿勢をそのまま抱いている傾向がある(反り返り姿勢が増長され、長引くことになる.)~ 強いと、上肢は肩関節外転・肘伸展位を呈しやすい.
・ 引き起こし反応では、股関節が伸展し、診察医側にずれたりする.あるいは、立ち上がってくることもある.
・ 仰臥位姿勢・運動を観察すると、四肢の屈曲位を呈し得る 末端手足の動きには、質・量とも問題がない.
・ 痩せ型で筋緊張の亢進している児、SFD児に多い傾向がある.歩行開始はむしろ早くなる傾向がある.
・ 上肢を体前方に置いた屈曲位抱きを指導する. ~ イメージは「坐位姿勢を抱く。手は前で合わせて
反り返り傾向のある乳児においては,保護者は反り返り姿勢をそのまま抱いていることが多い(図4).育児指導のポイントは,「座位姿勢」で抱くこと,仰臥位での屈曲位姿勢での遊び,即ち,月齢に応じて hand to kneeやhand to foot 姿勢をとらせて,少しの揺らしを与えたりしつつ,あやしかけたり,或いは,大人が足方に位置して児の両足を持って屈曲位を取らせ,イナイナイバーをしたりすることである.
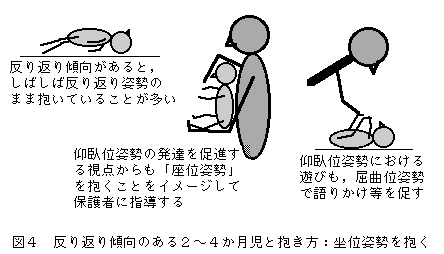
なお,反り返りの強い例では,生後4か月を過ぎても,引き起こし反応において体幹が垂直になっても頭部が後屈したままのことがある.この場合,頚定の遅れや脳性麻痺の可能性があるとして,発達診断を求められる.しかし,座位姿勢や腹臥位懸垂,斜位懸垂では頭部は安定して,立ち直りを見せていることが多く,発達変異の評価となる.運動発達の個性の違いであって,異常ではなく,遅れでもないことを説明し,座位姿勢抱きを指導することになる.
這いの発達と個人差
這う・這わないは発達の異常を論じる根拠にならない.即ち,腹臥位姿勢自体を嫌って這いに至らない例(図5),這わないで立位化に至る例など,個人差が大きいためである.
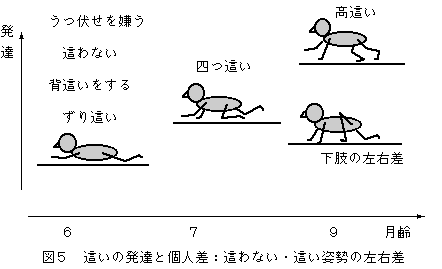
一般的な這いの発達は,“ずり這い(匍匐)”から“四つ這い”,さらに“高這い”であるが,中には“背這い”をする例もある.また,片方の膝を立てて,明らかな左右差のある這いを呈する例もある.
正常児において,這いを誘発する環境調整は望ましいが,這わないからとして,保護者がストレスを感じたり,嫌がる児に対して強制させることは不要である.
ただし,発達障害児においては,這いを誘発することは重要であり,療育プログラムに取り入れている.
下肢を突っ張らない例
生後7か月を過ぎると,第2伸展期に入る例が多くなる.一方,8~10か月になっても下肢を突っ張らないことを心配しての相談例が少なからずある.
こうした例の特性を表2にまとめた.家族歴が陽性の例も散見される.もっとも特徴的といえるのが,座位移動を行う児,即ち,シャッフリング(shuffling)児であり,歩行開始が2歳頃に至ったりする.
発達診断上の要点は,知的障害の可能性に関してであり,かつ,その有無に関わらず,保護者を含めた発達支援,適切な指導が欠かせない.その基本は保護者の安心にある.
表2 下肢を突っ張らない例(shuffling infant)の特性
・ 筋緊張低下(傾向)が必須
・ 肥満体型:いわゆる堅太りでない.ぶよぶよ太りの児
・ 初期所見:うつぶせ姿勢を嫌う.
・ 屈曲期に留まり、第2伸展期への移行が遅れる.
・ 立位化の遅れ:歩行開始の遅れ(傾向)~ 程度による.
・ 坐位姿勢での移動手段を獲得:シャッフリング児
・ 知的障害児が混入しうる 例)ダウン症候群児 Prader-Willi症候群
・ シャッフリング児の家族歴があり得る.
・ 低緊張型の脳性麻痺は重度であり、シャッフリング獲得に至らない .
母趾の発達
立位姿勢から歩行獲得に至る過程で,母趾の発達に変化が認められる(図6).即ち,新生児期には原始反射である足底把握反射が認められ,まもなくこれが消失する頃,母趾背屈位が基本となる.これは,這い易い肢位であり,他の哺乳動物において認められる肢位でもある.

やがて,立位姿勢をとるようになると,新生児期の把握反射のごとく,母趾は底屈し床面を押さえる.ただし,その状態では立位姿勢の保持に留まり,伝い歩きには至らない.或いは,伝い歩きに必須であるホッピング(hopping)反応も出ない.立位姿勢が安定する頃に,母趾の底屈は止み,ホッピング反応が現れる.とくに,後方へのホッピング反応は重要であり,発達変異か痙性麻痺徴候を診断する根拠にもなる.
新生児~乳児期に生理的に出現し,大人では異常反応であるバビンスキー反射は,この頃から消失していき,実用歩行獲得段階で消失する.さらに,運動能力が高まると,例えば,短距離走のスタート時など,われわれは母趾背屈位を効果的に用いることになる.
つま先立ちを考える視点
生後9~12か月頃に,立位姿勢はとるが“つま先立つ”ことの訴えで発達診断を求められる例を経験する.痙性麻痺が軽い場合,立位化を獲得する1歳頃から尖足傾向が出始める.これと,発達変異なのか否かが問われる.
その鑑別に有効なのが,斜位懸垂時の下肢の反応(図7)と後方ホッピング反応である.
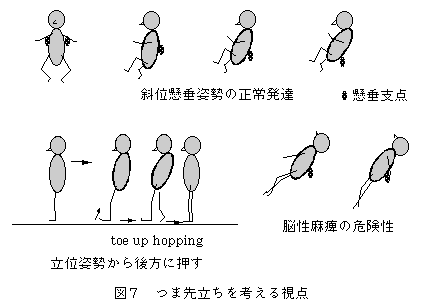
対象児を正中位に抱き上げ,急に左下ないし右下に傾けると天井側の股・膝関節が屈曲し,足関節が背屈位をとる場合が正常である.
また,リラックスし足蹠を着地させた立位姿勢の状態から,急に上体を後方に軽く押すと,母趾を床面から挙上させて,一側の下肢が後方に立ち直る場合(toe up hopping)が正常,かつより歩行獲得に近い発達段階にあると評価出来る.それを獲得する前段階では,両母趾の一瞬の挙上のみに留まる.
一方,痙性麻痺のある場合,急な斜位懸垂位を負荷すると,下肢は伸展し,尖足位を呈し得る.かつ,toe up hopping も見られず,母趾はむしろ床面を把握する.
なお,腋窩懸垂から床面に降ろすと,痙性麻痺では尖足が出現し,尖足位強まるが,ときに,発達変異例でも尖足位が出現し,軽い痙性麻痺との鑑別に困惑することがある.この場合,斜位懸垂での反応,toe up hopping の有無が有用となる.
総括および乳幼児健診と地域的システム
1次健診での運動発達の診察のポイント:
健診の時期は,一般的に,先天異常の有無,股関節の状態に関する評価および母親・家族の育児不安等の把握と支援を主目的とした1か月前後と,頚定獲得期の3~4か月,座位獲得期の6~7か月,立位化の始まる9~10か月で行われることが多い.そして,それらの健診での評価は図8に示した方式で対処されることになる.健診の時期は,一般的に,先天異常の有無,股関節の状態に関する評価および母親・家族の育児不安等の把握と支援を主目的とした1か月前後と,頚定獲得期の3~4か月,座位獲得期の6~7か月,立位化の始まる9~10か月で行われることが多い.そして,それらの健診での評価は図8に示した方式で対処されることになる.
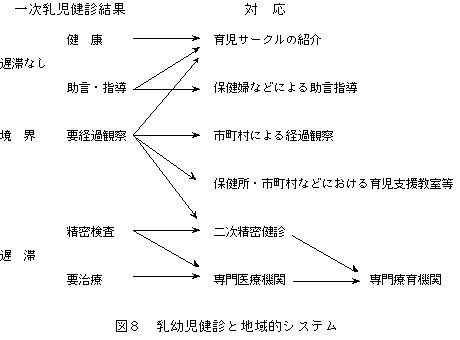
運動発達障害を呈する病態は多様であり,これらを見逃さないことも大切であるが,発達障害の疑い例,とくに,疑陽性(false positive)例が過剰になっても困る.少子化時代において,きめ細かな育児支援が求められる時代にあり,かつ,被虐待(child abuse)が社会問題になっている昨今であるが故に,的確な発達診断および運動発達を促す子育て支援が願いとなる.
おわりに
本稿は,総説枠の特性上,乳児の運動発達の基本を踏まえた上での留意点を主体とした断片的な記述に留まっていることを承知している.鳥取県では,健康対策協議会母子保健対策専門委員会委員が執筆した乳幼児健診マニュアルを作製しているのでご活用願いたい.乳児健診初心者には写真解説の多い前川の著書が有用であろう.
文 献
1)大谷恭一,安東吾郎,北岡宇一 他:鳥取療育園10年間のまとめ.鳥取医誌.14:120-126.1986.
2)大谷恭一,坂口恵津子,井上潤一 他:鳥取県東部地域における運動発達障害児の療育-鳥取療育園の現状と展望.鳥取医誌.19:158-162.1991.
3)大谷恭一,坂口恵津子,井上潤一 他:鳥取療育園における外来療育の実践と効果.鳥取医誌.21:161-165.1993.
4)大谷恭一:発達障害児通園施設の動向と展望.鳥取医誌.27:150-154.1999.
5)鳥取県乳幼児健康診査マニュアル,平成10年度版.鳥取県福祉保健部.1998.
6)前川喜平:写真でみる乳児健診の神経学的チェック法,第4版.南山堂.東京.1995.
小生は智頭病院に異動後、一次の健診の場で、発達診断も常に含め、抱き方に始まり、子育てに係る工夫などを提案し、安心の啓発をした上で、必要な例では、保護者ニーズを優先し、保健師が調整し、不定期の健診機会を設定しています。
_/ _/ _/
乳児の運動発達の本質は変わりません。読み直し、軸ブレはなしとして、温故知新に up しました。とにかく、保護者の安心が最優先です。発達の個性を理解し、具体的なお話をしています。
2020/6/15(月)当直の夜~翌早暁に。